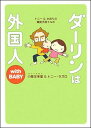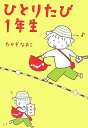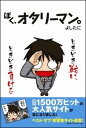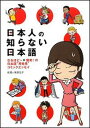[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただただクリックするだけのブログパーツです。一目見て、そのそのデザインにグッときました。どう見ても「アレ」です。
もう1つ、こんなのも見つけました。上に貼り付けたものほど有名ではないかもしれませんが、わかる人にはわかるはず。やはりグッと来ます。
○YOUSUCK
ブログパーツ「クリックバトラー」を配布しているサイトです。他にもブログパーツがあります。
http://www.yousuck.jp/index.html
ウォーキングや筋トレ、英会話など新しい習慣を身につけるのは大変なものです。「三日坊主」なんて言葉が頭をよぎり、はじめの勢いはどこへやら、初志貫徹とは程遠い竜頭蛇尾な結果になりがちです。
そんな「三日坊主」癖の人向けのツールがグーグル・ガジェットとして「やった!?」が公開されています。
○グーグル・ガジェット「やった!?」説明ページ
http://tmyymmt.mine.nu/yatta/
使い方は簡単です。日付が横にずーっと続くカレンダーに並び、縦に項目が書かれた表になっていて、該当項目をその日に実施したならクリックするだけ。クリックすればそのマスの色が変わり、その日に実施したことがわかります。詳しくは、上でリンクを貼った説明ページを見てもらうのがいいと思います。
これを見たときに連想したのが「Don't Break the Chain」。内容としては「やった!?」と同じようなもので、祖先に当たるものです。
「Don't Break the Chain」は「ライフハック」の分野でもてはやされていたツールで、「Don't Break the Chain」で検索をかけると日本のライフハック関連サイトが多数出てきます。
○「Don't Break the Chain」トップページ(英語)
http://dontbreakthechain.com/
(今知ったのですが、「Don't Break the Chain」もグーグル・ガジェットになっていたのですね。僕が知った当時にはガジェット化されていなかったように思います。)
「やった!?」にしても「Don't Break the Chain」も「続く」ことを主眼に置いたツールです。「続く」と快感になりますし、「続かない」とストレスになります。
これって、卓球やテニス、バドミントンなどのラリー競技に似ています。ラリーも「続く」と楽しくなってきますし、「続かない」とこれほどつまらないこともありません。
卓球やテニス、バドミントンなどでラリーを続けるには技術が必要です。相手が打ち返しやすい球(シャトル)を打ち、相手も自分が打ちやすいように球(シャトル)を打ち返す。そんな呼吸がラリーを続けるコツです。
そういえばニンテンドーDSで発売されている脳トレソフト『脳を鍛える大人のDSトレーニング』とか『えいご漬け』とか『漢検DS』なんかにも、「Don't Break the Chain」と同じようなカレンダーが表示されます。これらソフトには「ラリーを続けるための相手」はいませんが、「続く」ための工夫が施されています。
ここで挙げた3本のソフトには「得点」が存在します。『脳を鍛える~』には「脳年齢」という得点が存在します。『えいご漬け』『漢検DS』には「級」が存在します。「脳年齢」や「級」を上げていくことがモチベーションアップにつながり、毎日続ける動機となります。しかも、これらの得点は1日に1回しか測定できません。これがもどかしくて、つい続けてしまうのです。
これに加えて、この3本とも最大4人までセーブデータを保存することができます。ラリーの相手ではありませんが、同じ目的を持った同士として一緒にがんばることができます。
こうしてみると「脳トレ」は「脳トレ」だから流行ったのではなく、「続く」ための工夫が練られていたから流行ったのだろうと推測できます。続かないことには流行しようがありませんから。
新しい習慣を始めるのは、相手のいない「壁打ちテニス」のようなものです。相手がいないから、続くか続かないか、すべて自分がカギを握ります。いや、むしろ、続けるのも続けないのも、すべて自由です。決める権利があるのです。だからこそ「三日坊主」に陥ってしまうのです。
「やった!?」も「Don't Break the Chain」も、どこか惜しいという思いがあります。記録としての機能は果たしているのですが、続けるのを応援するツールにはなっていないのです。「壁打ちテニス」なのです。(○日連続を表示する機能はあるようですが)
「続ける」のって難しいですね。
(そういえばこういったツールって、常備する携帯アプリの方が向いているような気がします。もうあるのかもしれませんが。)
※2009年6月18日追加
○自分のブログ記事「やらないことを続ける?」
ここで書いた「新しい習慣を続ける難しさ」の続きにあたる内容です。
http://tblb.blog.shinobi.jp/Entry/71/
以前、「地球のサイズを1mに縮めると」なんていう記事を書きました。もしも地球の直径を1mに縮めたら、月や太陽の大きさはどうなるのか、太陽までの距離はどのくらいになるのか、といったことを計算したものです。
計算そのものは単純な比例式なので、機械的に電卓をたたき続けるだけです。頭を使う、というほどの内容ではありません。それにもかかわらず、あろうことか式を立て間違えていたのです。頭で式を立てていたがために、単位換算を誤っていたようなのです。オーダーがひどくずれていました。まあ、なんと情けないことか。
あわてて計算しなおし、訂正しました。
見た人はそう多くはないでしょうが、念のためにここにも記しておきます。
なんだか最近、書店で「エッセイマンガ」を見かけることが多くなっている気がします。『ダーリンは外国人』(小栗左多里・著、メディアファクトリー)や『ツレがうつになりまして。』(細川貂々・著、幻冬舎)が出版され出した頃からその傾向がありましたが、最近その傾向が強まっているのを感じます。『ツレがうつに……』は、今度NHKでドラマ化(※)されるようですし。
(※) あの絵のタッチのおかげで「ウツ」という重いテーマが清濁まとめて受け止められることを思うと、実写化したとき「重さ」だけが強調されるのではと不安なのですが。もしくは、単純に苦労&成功物語化してしまいそうで……。脚本を引き受けた作家の度胸に感服します。
エッセイマンガの点数が多くなり、本屋の一角を賑わせています。「出版不況」なんて言われている昨今で、どれだけ売れているのかはわかりませんが、出版点数をみる限りでは密かなブームが起きているのは間違いないようです。
出版されるまでにすでに選別が行われているからでしょうか、アイデアに富んでいます。しかし、アイデアに優れているばかりに不安がよぎります。このうち何人の作家が生き残るのだろうと。
エッセイマンガというのは、そのエピソードの面白さだけで充分魅力を発揮します。エピソードそのものが面白いからです。
けれども、「エピソードの面白さ」だけでこの業界で生き残れるのでしょうか。疑問が湧いてきます。
「エピソードの面白さ」だけだったら「替え」はいくらでもいると思うのです。変な話、出版社側の立場にしてみれば若い人の方が原稿料を安く抑えられるわけです。「エピソードの面白さ」にしか魅力がなければ、次から次と新人を投入する方が効率的であるように見えます。
せっかくこうやって日の目を見ているのですから、実力を付ける努力をしてほしいと思うのです。又とないチャンスを逃してほしくはありません。画力は上げてもらいたいです。コマ割りに工夫を感じられない作家も多く見られます。セリフ回しもまだまだ工夫ができると思うのです。
「描けない人」が偉そうに講釈を垂れる資格は本来ないのですが、つい書きたくなりました。エッセイマンガの作家さんたちがこの先もエッセイマンガを続けていくにしろ、ストーリーマンガを描くにしろ、実力を付けないことには職業として続けていけません。「次を読みたい」という期待の裏返しとしての講釈だと考えてください。
最近読んだ(まあ、本屋での立ち読みで誠に恐縮なのですが)エッセイマンガを何点か取り上げておきます。
『ひとりぐらしも9年め』
著者:たかぎなおこ
発行:メディアファクトリー
この『ひとりぐらし』シリーズの他にも、『浮き草デイズ』(1)(2)(文藝春秋)、『150cmライフ。』(1)~(3)(メディアファクトリー)、『ひとりたび』シリーズ(メディアファクトリー)など数々のエッセイマンガを書いているたかぎさんの新作です。
たかぎさんの「ゆるさ」は、1つの芸だと感じます。
自分の「弱さ」を隠すことなく描きます。「だらしなさ」も「いいかげんさ」といった「弱さ」をそのまま描きます。その「弱さ」は、多分、ほとんどの人が持っている「弱さ」で、それを隠すことをしません。だから、どこか親近感が湧いてくるのでしょう。弱いのは自分だけではないんだと安心できます。この安心感と作風が相まって「ゆるさ」が演出されます。
それにしても、ビールを飲む姿が印象的です。何とも幸せそうに飲んでいます。どんなコマよりも気持ちがこもっているのを感じます。
『結婚式っておもしろい!?』
著者:たかはしみき
発行:主婦と生活社
本屋で見つけて夢中になって読んでしまいました。
いや、「結婚」なんて、まだまだ縁のない話です。けれども、結婚を巡る苦労が赤裸々に描かれていて、その生々しさに引き込まれてしまったからでしょう。時を忘れて読みふけってしまいました。
多くの人はそうだと思うのですが、多分、このマンガを読むと、登場人物を自分に置き換えてしまうのではないでしょうか。来るべきに備えて脳内シュミレーションを行っているのだと思います。この苦労は他人事ではない。その思いが夢中にさせてくれます。
途中の波瀾万丈でドキドキさせてくれるのですが、締めくくりが爽やかに終わってくれるので、読者としては救われます。
いよいよ結婚が決まるぞというカップルにこの本を贈ったら、喜ばれるのではないでしょうか。肝が据わって、苦労を乗り越えてくれそうです。
それはさておき、この本には「発行日」が書かれていないのに気付きました。
日本の書籍には「発行日」が書かれていることが多いのですが、そういう決まりは存在しないそうです。「発行日」を書くのはただの慣習。
この『結婚式って……』に「発行日」が書かれていないのって、意図的なのでしょう。営業的な戦略を予感させます。
『理系クン』『理系クン 結婚できるかな?』
著者:高世えり子
発行:文藝春秋
結婚つながりでもう1冊。「理系クン」を文系彼女から見たエッセイマンガです。1冊目の『理系クン』でカップルとしての様子が描かれていましたが、2冊目の『理系クン 結婚できるかな?』でついに婚約しました。なんともおめでたい話です。
「理系」の僕としては、何とも身につまされるマンガです。ここに描かれる「理系クン」が他人に思えません。
このマンガを読むと「理系クン」の思考がつかめます。理屈っぽくて、自分の趣味嗜好に忠実で、アルゴリズムで物事を処理したくなり、意味の有無で価値判断をしてしまう。自分はこんなに極端ではない!と多くの「理系クン」は思うのでしょうが、他人から見たらこう写るのでしょうね。「理系クン」の一員として、ゾッとします。
もちろん、個人差はあるし、色眼鏡で見るのもいけませんが。
『理系の人々』(よしたに・著、中経出版)も同じ「理系クン」系統の本ですね。こっちはこっちで違う方向の極端ですが。
(『ぼく、オタリーマン。』シリーズが100万部突破だそうで。これはすごい!)
『日本人の知らない日本語』
著者:蛇蔵、海野凪子
発行:メディアファクトリー
このマンガは原作者(海野凪子さん)と漫画家(蛇蔵さん)が別の人というものです。エッセイマンガでは珍しいです。原作者である日本語講師が1つのキャラクターになっていて、魅力的な存在になっています。
エッセイとして自分のことを自分で描くと、どこか照れが出てしまいます。けれども、このマンガでは照れを出すことなく突き抜けていて、それがいい塩梅に面白さを誘発しています。
『ダーリンは……』『日本人の……』と2つのマンガを読むと、言葉にこだわりを持った外国人はそのこだわりだけで充分面白いのがわかります。「そこが気になるのか!」というのが新鮮です。そのこだわりに翻弄されている姿が笑いを誘います。
印象に残ったマンガを書き記しました。他にも読んだものはあるのですが、あまり印象に残っていません。これからも「エッセイマンガ」を追いかけ、応援していきます。
ちょっとした思い付きです。
切符に書かれた4つの数字を組み合わせて10にするパズルがあります。それの応用です。
1~10までの同じ数字5つを組み合わせ計算して5にしてください。使えるのは+-×÷とカッコだけです。√や小数点、!は使いません。
1 1 1 1 1 = 5
2 2 2 2 2 = 5
3 3 3 3 3 = 5
4 4 4 4 4 = 5
5 5 5 5 5 = 5
6 6 6 6 6 = 5
7 7 7 7 7 = 5
8 8 8 8 8 = 5
9 9 9 9 9 = 5
10 10 10 10 10 = 5
1や5を5にするのはあまりにも簡単です。一方、2や9、10を5にするのは工夫が必要です。なかなか骨が折れます。
(主に小学生に対して)頭の体操として出題するのにいいかもしれません。解ける喜びと悩む喜びの両方を提供できる問題になっているかと思います。
自分のアンテナに引っかかった面白いもの、興味惹かれるものも収集して記録しています。
不定期連載です。気の向いたときにお立ち寄りください。
http://bookdiary-k.blogspot.com/
| 06 | 2025/07 | 08 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |